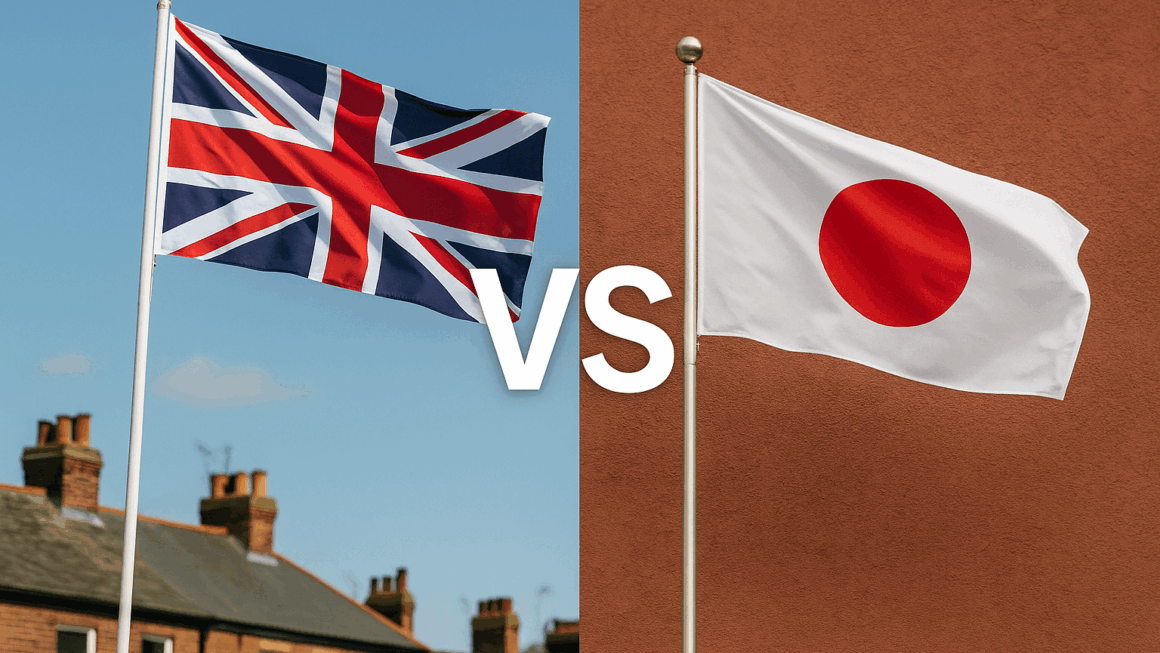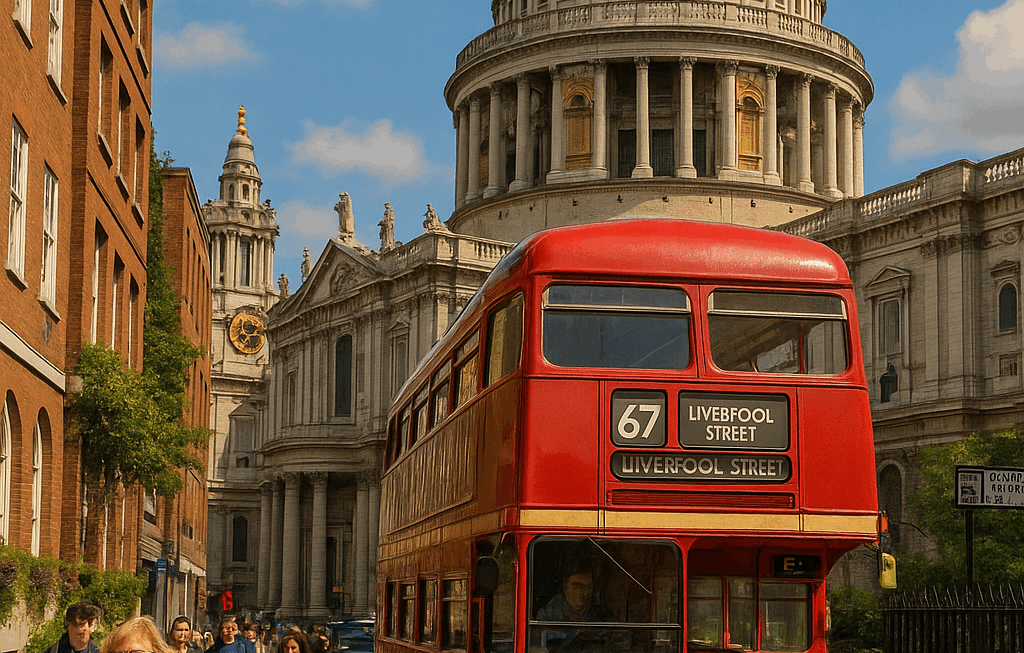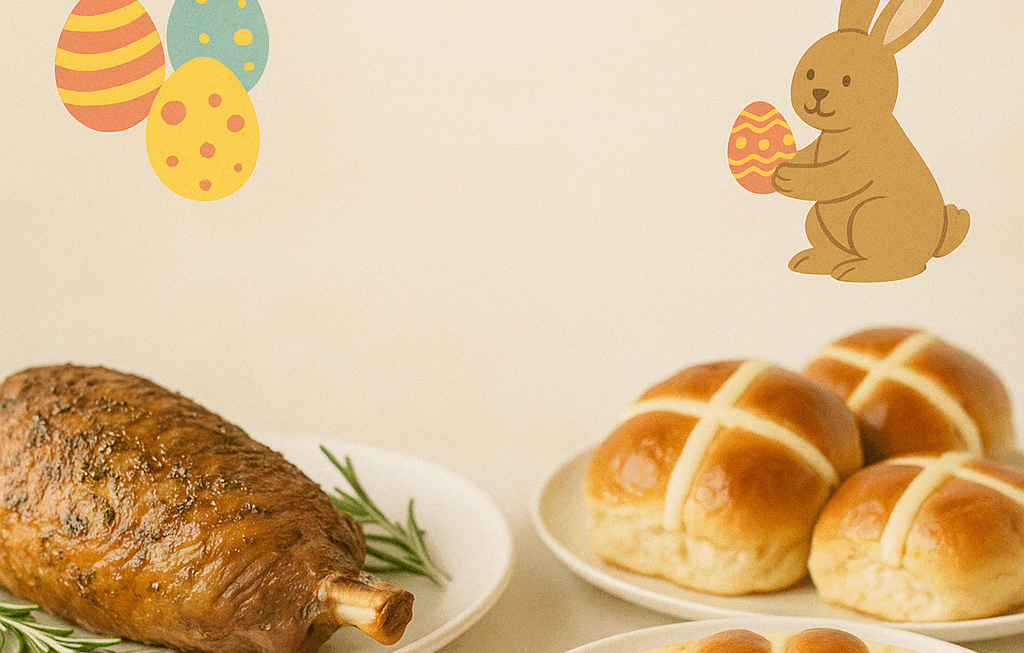「えっ、もう退院?」
日本での感覚からすると信じられないほど、イギリスの入院期間はとても短いです。特に出産のときなんて、早朝に赤ちゃんを産んで、その日の夕方には退院することも。
私はイギリスでOT(作業療法士)として働いていますが、NHS(国民保健サービス)での入院と退院のスピード感には、最初かなり驚かされました。(NHSについては以前の記事「日本と違う?イギリスの医療事情」をご参考下さい😊今回の記事では、日本との違いや、現場での退院調整のリアル、そしてOTとして関わる役割についてお話しします。ちなみに今回書いているのはNHSの病院の事であって、プライベートの病院の話になると全く違ってきます。
🤱 出産後も翌日には退院!?
日本では、出産後に5〜7日ほど入院するのが一般的ですよね。
病院や産院によって違いはあるものの、産後の体の回復や授乳、沐浴の練習まで、しっかりサポートしてくれます。
妹が出産した時の病院食があまりにも豪華で、話を聞いてるだけで羨ましくなったのを今でも覚えています🍽️
一方、イギリスでは問題がなければ翌日には退院。帝王切開でも平均2日ほどです。
ちなみに、イギリスの入院期間の短さを象徴する出来事といえば、キャサリン妃の出産後の退院です。
第2子のシャーロット王女のときなんて、朝8時半に出産して、その日の夕方には退院。出産から約10時間後には、きれいなワンピース姿で病院の前に立って、笑顔で赤ちゃんをお披露目していました。
第3子のルイ王子のときは、さらにすごくて、出産からわずか7時間で退院しています。
しかも、どちらの時も退院前に完璧なヘアメイクと服装でにこやかに手を振っていて、まるで雑誌の表紙のような姿。出産したばかりとは思えないくらい華やかでした。
私はというと、出産直後は完全に魂が抜けていて、生ける屍のような状態。ぐったりして、誰にも話しかけられたくないモード全開でした。あの姿で笑顔でカメラに手を振るなんて、もう尊敬を通り越して異次元です。。。
🏡 「病院は医療処置を受けるところ」
イギリスでは、病院は基本的に「医療処置を受ける場所」という考え方。
治療が終わっているなら、あとは家で休んだ方が安全で快適、というのが前提になっています。
病院は感染症リスクもあるし、体が弱っている人ほど、早く家に戻った方がいいとも言われているんです。
ちなみに私も早く帰りたい派です🧳
相部屋で落ち着かない、食事はいまいち、トイレやお風呂も気を遣う…💦
🛏️ リハビリ病院はまた別の話
リハビリ病院(Community HospitalやRehab Unit)は、“機能回復”が目的の場所。
ドクターが常勤していないことも多く、週に数回、コンサルタントやGPが様子を見に来ます。
処置が必要であれば、退院後も地域のナース(District Nurse)が訪問してくれます。
💰 NHSの短い入院には「お金の事情」もある
NHSでは患者に費用の負担がない分、病院側は限られたリソースで多くの人を診なければなりません。
だから、医療処置が終わった人には、できるだけ早く地域での支援に切り替えてもらう必要があるんです。
ちなみに実際の入院コスト(1泊あたり)
- 一般病棟:£400〜£700
- 手術系・脳神経系病棟:£700〜£1,200
- ICU(集中治療室):£1,500〜£2,500
- リハビリ病院:£200〜£400
これだけコストが高いとなると、不要な入院を避けるのは当然ですよね。
👥 退院支援はチーム戦!
私が病院で働いていたときは、毎朝「信号システム」に基づいたMDT(Multidisciplinary Team=多職種チーム)のミーティングがありました。メンバーはドクター、Discharge co-ordinator,病棟の看護師リーダー、PT ,OT,ソーシャルワーカーです。ちなみに、このDischarge Coordinatorとのやり取りで私がしんどかった時期については、以前の記事でも書きました。→ OTとして病棟勤務していた頃、辛かったこと
- 🔴 赤:医療処置がまだ必要
- 🟡 黄:まもなく処置が終了予定
- 🟢 緑:医療的には退院OK!
私が働いていた病院ではOTが関わるのは黄色から。赤のうちはまだ体力的にも難しいし、退院の目処もついていない状態です。
🛠️ OTとしての役割
黄色の段階で「退院に向けて何が必要か」を整理します。
リハビリが必要ならリファーラル、自宅なら福祉機器やケアの手配など、OTの出番です。
🏠 具体的な退院支援の流れ(例)
例えば、股関節の手術を受けた方がいたとします。
入院前は2階建ての家に一人で住んでいて、買い物も全部自分でしていた。
でも今は体重をかけるのがやっとで、家族もいない…。
🛁 OTの生活動作アセスメント
まずはシャワーやトイレ、ベッドからの起き上がりなどが一人でできるかを確認します。
トイレや椅子の高さを調整することもありますし、
お風呂が難しい場合は、perching stoolを使ってキッチンでスポンジ洗いを提案することもあります。
🧗 PTの階段練習、OTの環境調整
階段がある家ならPTが階段練習を行い、難しければOTが1階での生活に切り替える提案をします。
🧑🤝🧑 地域支援へのバトンタッチ
退院後に支援が必要なら、Reablement teamやIntermediate care teamにリファー。
最長6週間の無料サービスで、在宅生活への移行をサポートします。
🔗 OTは病院と地域をつなぐ橋渡し
退院前にはDischarge Coordinatorのもとで、
各職種が連携して「安心して帰れる準備」を整えていきます。
その中でOTは、病院と地域のケアの“橋渡し役”として、重要な存在なんです。